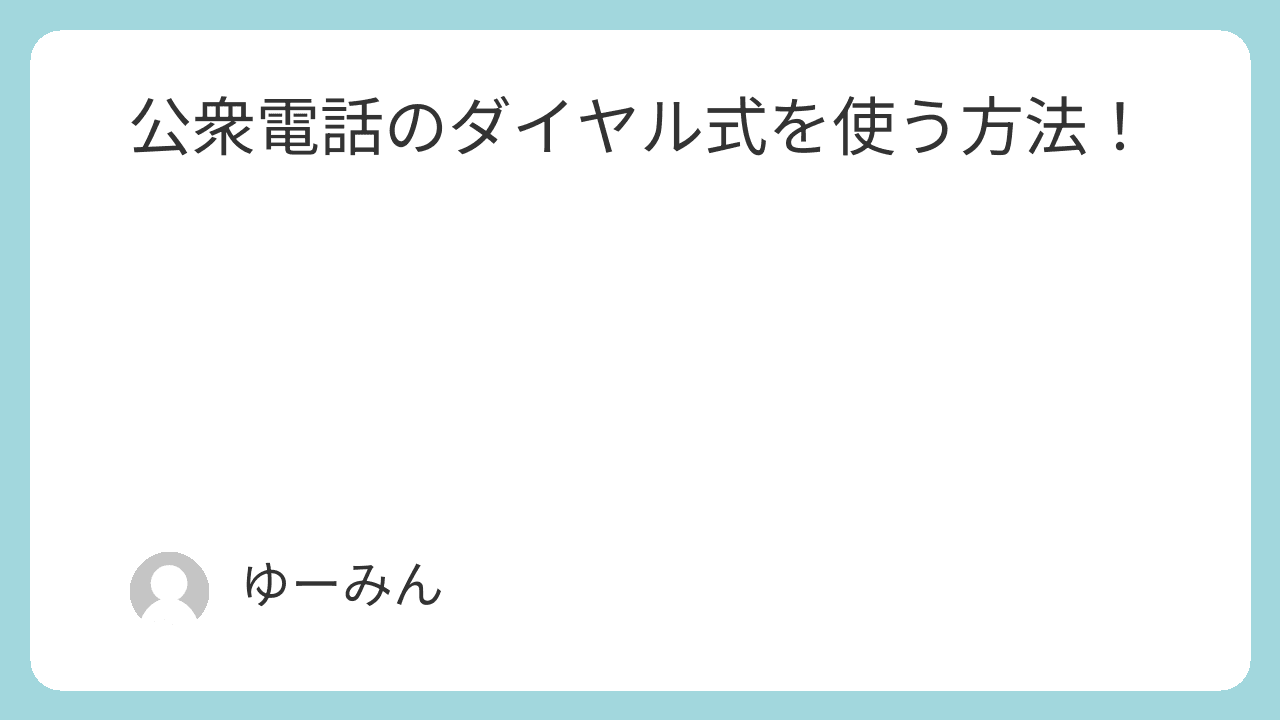今はほとんどの人が携帯電話を使いますし、家庭の電話もボタン式が一般的です。
だから、ダイヤル式の電話を見かける機会はほとんどなくなりました。
それでも、一部の公衆電話ではダイヤル式が残っていることがあります。
いざという時に困らないように、ダイヤル式の操作方法を覚えておくことは大切です。
ここで、ダイヤル式電話の基本的な使い方をお教えします。
操作は以下の通りです。
- 受話器を持ち上げる。
- 10円玉を入れる。
- 電話番号をダイヤルする。
これで完了です。
詳しいかけ方を解説していきます。
昔の公衆電話でのダイヤル式の操作方法

「ダイヤルを回す」とは、番号を選んで、その穴に指を入れ、時計回りに回して数字を入力する行為です。
昔の人々は今でも「電話を回す」と表現することがありますが、その言い方は少なくなっています。
ダイヤルを回す際は、ストッパーまで回してから指を離します。
指を離すと、ダイヤルは自動で反対方向に回って元に戻り、それが一つの数字を入力したことになります。
電話番号が7桁であれば、この動作を7回繰り返します。
プッシュ式のボタンと比べると、ダイヤル式は時間がかかり少し手間がかかります。
「1」や「2」のような数字はすぐに元の位置に戻りますが、「0」や「9」のような数字では戻るのに時間がかかり、現代の感覚では少しイライラするかもしれません。
操作の流れは以下の通りです。
- 受話器を持ち上げる。
- 「ツー」という通話可能な音がするか確認する。
- 目的の電話番号をダイヤルする(ストッパーまで回し、指を離すと自動で戻る)。
- 全てのダイヤルが完了すれば通話が開始されます。
受話器を上げた時に「ツー」という確認音がなければ、使えない状態ということなので注意が必要です。
そういう場合は一度受話器を置いてから再度受話器を持ち上げると通話可能になってることが多いです。
また、受話器を上げたままにしておくと「ツー」という音が途切れて通話不可能な状態になることもあります。
時間切れにならないようにしましょう。
そのためにも、受話器を上げ始める前には相手の番号を確認しておくのが賢明です。
これでダイヤル式電話の基本的な使い方の説明は終わりです。
公衆電話トラブル対処法
- ダイヤルが途中で止まった場合は、一度受話器を置いてからやり直します。
- 通話中に相手の声が聞こえにくい場合は、受話器の音量調節ツマミで調整できます。
- 硬貨が詰まった場合は、無理に取り出そうとせず、電話機に記載された連絡先に通報しましょう。
公衆電話の料金システム
公衆電話での通話料金は、全国一律で10円で56秒間通話可能です。
緊急時の使用方法
災害時や緊急時には、公衆電話は無料で使用できる場合があります。
110番(警察)、119番(消防・救急)への通話は、硬貨を入れずにダイヤルすることができます。
また、災害時には、NTTの「災害用伝言ダイヤル(171)」も無料で利用可能です。
公衆電話での市外局番は必要?その疑問に答えます!

現代の携帯電話を使う際は、近所の人の家に電話をかけるときでも市外局番を入力するのが普通です。
同様に、市役所や区役所、学校などの公的機関に電話をかけるときも市外局番が必要とされています。
携帯電話ではどこにかけるにしても市外局番を先にダイヤルするため、公衆電話を使う時に市外局番の入力が必要かどうか迷うことがありますね。
実は、同一市内での通話の場合、公衆電話からは市外局番を入力する必要はありません。
たとえば、学校から自宅にかけるときや、地元の友人や病院に電話する際は、普通の家庭用電話と同じ方法でかけることができます。
しかし、隣町や他県など遠方に電話をかける場合は、市外局番を入力する必要があります。
ダイヤル式電話の歴史と利点

ダイヤル式電話は昭和の初めから広く使用され、シンプルな機構で故障が少ないという利点がありました。
停電時でも使用できる機種が多く、災害時の通信手段として重宝されました。
現在でも、一部の施設や緊急時用の電話機としてダイヤル式が採用されているケースがあります。
まとめ
ダイヤル式の電話は、固定電話と公衆電話で使い方が同じです。
受話器を持ち上げ、お金を入れ、番号をダイヤルします。
ダイヤル式の操作に慣れていない人には少し難しいかもしれませんが、まだ使われている場所があるため、基本的な使い方を知っておくと便利です。